八幡西区地域に新しい合葬墓ができ、明日から本格的に案内開始となりました。
故人様の安寧を願って「なごみ霊廟」と命名しました。
金額などは今まで同様5万円です。


『こじんまり』でも『あたたかい』貸切り家族葬
八幡西区地域に新しい合葬墓ができ、明日から本格的に案内開始となりました。
故人様の安寧を願って「なごみ霊廟」と命名しました。
金額などは今まで同様5万円です。

みなさんこんにちは、総務部の奥島です!
エンバーミングについては本日で最後になります。
今回は実際にエンバーミングを必要とする場合についてご紹介していきます。
【ケース①】
亡くなられてからご葬儀まで時間がかかってしまう場合
悲しいことではありますが、人は息を引き取った時点から腐敗が始まってしまい、見た目の劣化が進んでしまいます。たとえ保冷庫やドライアイスを使っても凍結するということではないため、腐敗の進行をある程度抑えることができますが完全に止めることはできません。
そのため、亡くなられてからご葬儀を執り行うまでに日数がかかってしまう場合には、腐敗防止や見た目の維持という点からエンバーミングが施されます。
【ケース②】
海外から空輸でご遺体の搬送を行う場合
旅行や出張先で海外に行かれた方が亡くなられご遺体の状態で帰国される場合や、他国の方が日本で亡くなられてご遺体の状態で送還する場合などが例にあげられます。
このような場合、航空機を用いて海外からご遺体の搬送を行うため、安全上の観点からドライアイスを使うことができません。そのため故人様のご遺体を保全するためにエンバーミングが施されます。
【ケース③】
元気だった時の姿で見送りたい・見送られたい場合
長い闘病生活によって顔がやせ細ってしまったり、薬剤や点滴の影響で顔が膨張してしまったりすることももちろんあります。そのため、ご葬儀に参列してくださったご親族や友人・知人の方々が持つ故人様の生前の姿のイメージと違ってしまうこともあるかと思います。
特殊な状況でなくとも「元気だった時の姿でお別れをさせてあげたい」というご遺族の想いや「元気だった時の姿でお別れをしてもらいたい」というご本人の希望を叶えるために、エンバーミングを施すこともあるのです。
このように、エンバーミングが必要とされるシーンは様々です。
日本ではあまり聞かれませんが、世界に目を向けると多くの著名人や有名人のご遺体にエンバーミングが施されているそうです。
そして、実際にエンバーミングを利用された遺族の方々の満足度はとても高いようです。
大切な人の最期、苦しまれているお顔よりも穏やかなお顔を見て見送りたいと思う気持ちは誰しも同じだと思います。
この機会にみなさんもエンバーミングについて興味を持ってみてはいかがでしょうか。

みなさんこんにちは、総務部の奥島です。
本日はエンバーミングの基本的なことについてお話ししていきます!
エンバーミングは誰でもできるものではありません。
専門の資格を有する「エンバーマー」と呼ばれる人が、ご遺体の保存・防腐・殺菌・修復を目的に行うことができる特殊な技術なのです。
日本語では「遺体衛生保全」や「死体防腐処理」と訳されています。
エンバーミングは、ご遺体の消毒・殺菌を行った上で消化器官などの残存物の除去を行うほか、ご遺体の一部を切開して血液などを排出すると共に防腐剤などの保存液をご遺体に注入します。とても難しい内容ですが、こうすることでご遺体を10日間~二週間程度腐敗させることなく保存することが可能となります。
処置の流れを簡単に説明しますと、①ご遺体の状態を確認②消毒と洗浄③故人様の生前の姿に近づけるために洗髪や洗顔を行います。
そして、ご遺体の体内の処置にうつります。
最初にお話ししたように保全液を注入し、食道や胃などに残っている残存物を除去します。その後綺麗に縫合をし、再度全身の消毒を行い故人様が普段身につけられているような洋服を着付けたり、ご遺族様からの希望通りに着付けを行っていきます。
着付け後には改めてお顔の表情を整え、より生前の姿に近づけていきます。
故人様の体の処置としてエンバーミングと混同されてしまうのが「エンゼルケア」です。
エンバーミングは体内の処置まで行うのに対してエンゼルケアは故人様の表面的な姿を整えることを目的としているそうです。
ここまでエンバーミングの基本的なことや流れをご紹介しましたが、実際エンバーミングが必要となるケースはどういったものなのでしょうか。
次回はこの点についてお話ししていきたいと思います!
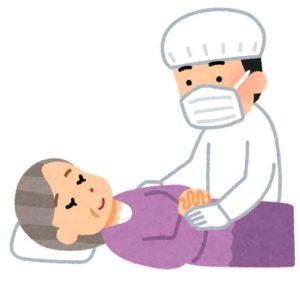
こんにちは、総務部の奥島です。
みなさんは「エンバーミング」をご存知でしょうか?
ドラマや映画の中で見たことがあるなというくらいで私自身も深くその内容は知りませんでした。
エンバーミングとは、ご遺体を消毒や保存処理、また必要に応じて修復することで長期保存を可能にする技法です。日本語では遺体衛生保全といいます。
日本では「火葬」が執り行われるためにあまり馴染みがない言葉かもしれませんが、土葬を主流としている国々では行われているご遺体保存技術です。生前の姿に近い形でお別れができるという点や衛生的な面から、近年日本でも注目されるようになっているそうです。
そこで今回は、エンバーミングの目的や手順などの基本的なことについてご紹介していきたいと思います!

皆さんこんにちは。
前回に引き続きブログを担当させていただく業務部の林です。
今回は弔辞とは何なのか、弔辞を作成する際のポイントについて詳しく書いていきます。
弔辞(ちょうじ)とは、故人様と親交の深かった人が霊前に捧げる故人様を弔う言葉の事を指します。
弔辞を作成する際のポイントとしては、一般的に弔辞の長さはゆっくり読んで三分程度、長くても五分以内にまとめると良いと言われています。
また、弔辞を作成する際、出来るだけ避けた方が良いとされている言葉としてご遺族様に挨拶する時と同様、不幸が重なるイメージを連想させる言葉や「死亡」といった直接的な言葉等の忌み言葉は弔辞でも避けた方が良いとされています。
弔辞と聞くとどうしてもきっちりとした固めの文章にするべきと思いがちですが、無理に難しい言葉を使う必要はなく、生前の思い出や故人様の人柄を偲ばせるエピソードを自分なりの言葉でまとめると良いのではないかと思います。
最後までお読み頂きありがとうございます。
これからもブログを書いていきますので次回も読んで頂けると幸いです。
それでは失礼致します。

皆さんこんにちは。
今回、直葬・家族葬の心響(こきょう)相生斎場のブログを担当させていただく業務部の林です。宜しくお願い致します。
皆さんは弔辞(ちょうじ)という言葉を聞いた事はありますか?
私は直葬・家族葬の心響(こきょう)に入社するまで弔辞を実際に耳にした事がありませんでしたが、働くうちに弔辞を聞く機会があり、その時の言葉がとても心に響きました。
そこで今回は弔辞についての記事をブログに書いていきたいと思います。

各会場のポップを少し作り替える事になり、改めて直葬・家族葬の心響(こきょう)の良いところを洗い出し。
久しぶりの心響会議。

本社で『餅つき大会』が始まるようですね。
餅大好きなので楽しみ。
しかし、出張の餅つき屋さんがあるとはビックリ。

コロナも落ち着きお店や食事に行く事も増えてきましたが、
やっぱり同じ行くならバーゲンセールはテンション入りますよね。
ブラックフライデー最高!

みなさんこんにちは総務部の奥島です!
弔電(ちょうでん)については最後になりますが、本日はより詳しい注意点をお話ししていきます。
先方へ必要事項を確認したら、弔電の手配を始めます。
その際に、気を付けるべき点です。
弔電に限らず、電報の文面には差出人の情報を記載します。
お名前のみでも可能ですが、実際の式で弔電を読む場合に司会者の方が読みやすいように、氏名等に読み仮名をつけておくと分かりやすく間違いも起こりません。また、ご遺族が把握しやすいように学校名、団体名、会社・部署名などの所属や肩書なども記載しておくと丁寧です。
併せて、ご遺族の方がお礼状などを出す際に手間がかからないよう、住所や連絡先も記載しておくことが望ましいとされいます。
弔電の文面は、故人様との関係性によって変わってきますがシンプルな一文のみでも構いません。
故人様と親しい間柄だった場合は、思い出や人柄がわかるエピソードなどを盛り込んだメッセージにすると、偲ぶ気持ちが伝わりやすいでしょう。また、ご遺族を労う一言を添えるのも良いと思います。
そして一番注意するべきことです。
弔電で使用を避けるべき忌み言葉として、直接的な「死去」といった言葉や、不幸が繰り返すことを連想させる重ね言葉にあたる「重ね重ね」「再び」、死や苦労を連想させる言葉「死」「苦しむ」、数字「四」「九」などがあります。
基本的に、不幸や不吉なことを連想させるワードは望ましくないということを意識することが大切です。
このように、弔電には色々なマナーがあります。
しかし事前に知っておけば、突然の訃報にも慌てず、故人を偲ぶ気持ちを十分に伝えることができます。
ぜひ今回ご紹介した内容を参考にしてみてください!
