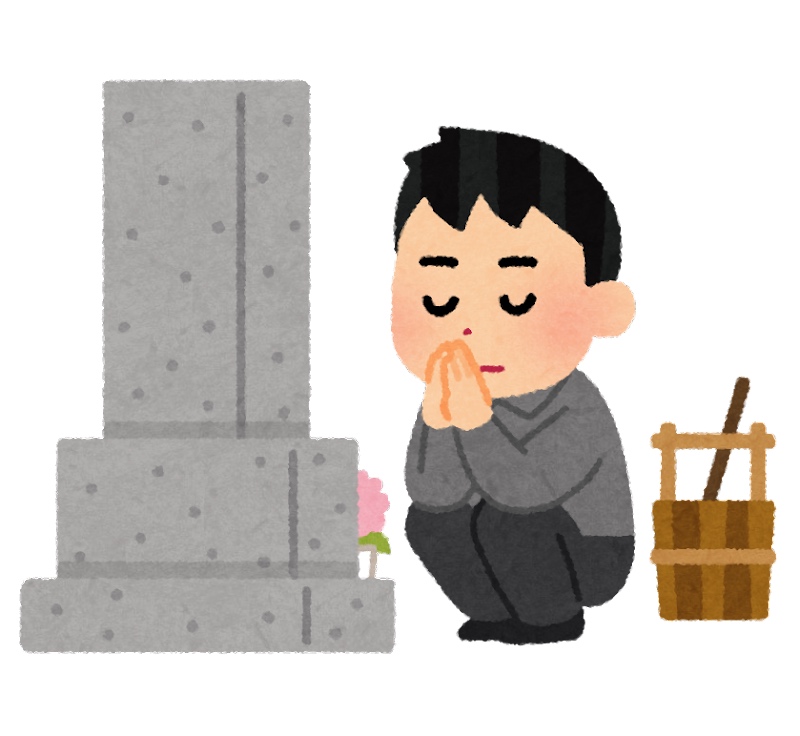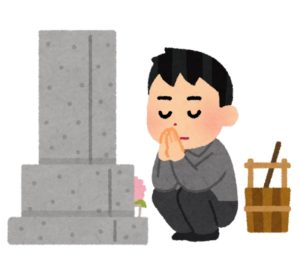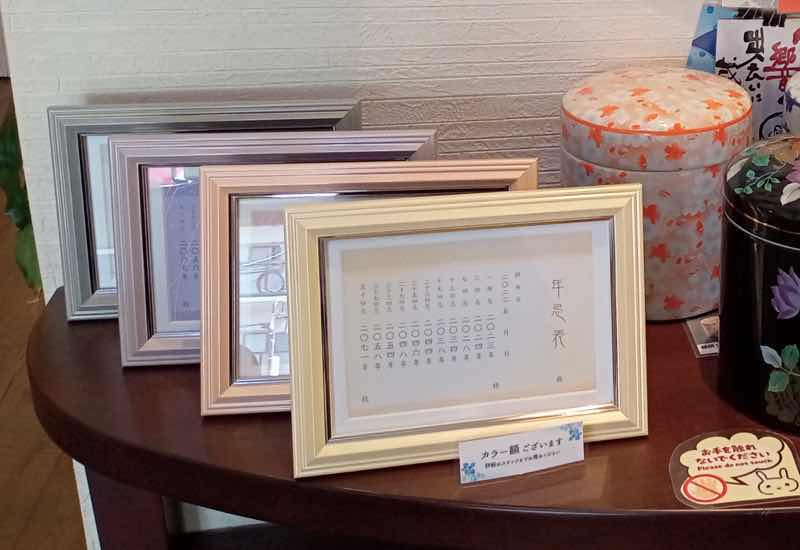引き続きブログを担当させていただきます、心響(こきょう)業務部の村橋です。よろしくお願いいたします。
今回のブログでは、エコアイスをお当てする際に気をつけている点と、指導を通して学んだことをお話ししていきます。
故人様にエコアイスを当てて差し上げる際に心がけている点として、まず故人様やご家族様の立場に立って考え行うことを大切にしています。日々の業務として慣れてしまうと、どうしても作業的になってしまう恐れがあります。ただ当てればいいと考えるのではなく「自分が故人様、もしくはご家族様だったらどう感じるか」を忘れずに意識して、丁寧にお当てするよう心がけています。
またエコアイス自体、無機質で重たい印象を受けてしまう物です。それをいくつもお体にお乗せする形になるので、ご家族様にとっては痛ましく感じられる場合もございます。そのため、ご家族様の前でエコアイスをお当てする際は、なるべく故人様にお掛けしているお布団や自分の体で隠しつつ、お体にお当てしている様子が見えないように行っております。
ここまでご紹介させていただいたエコアイスについての知識や当て方、心構え、心配りは先輩方にご指導をいただき学びました。その中で学び得た「基本を理解した上で状況に応じて対応を変える」「故人様とご家族様の立場に立って考える」「行動の意図を理解して行う」という三点は、ほかの業務を行う際においても共通して活かすことができるものだと感じております。
今後も引き続きこれらの学びを活かし、直葬・家族葬の心響(こきょう)での業務にしっかりと取り組んでまいります。

直葬・家族葬の心響(こきょう)では、故人様とご家族様に寄り添い、状況やご希望に沿って、一つ一つのお式を丁寧に精いっぱいお手伝いさせて頂きます。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。